実は自分はミステリー小説が好きで、今までかなりの数を読んできた。
今回は今までのミステリー体験をまとめてみる。
1. 江戸川乱歩の少年探偵団シリーズ
小学生のとき大好きだったのが江戸川乱歩の「少年探偵団シリーズ」。
特に冒険小説の色合いが強い作品が好きで、「大金塊」は繰り返し読んでいた。
でもそのなかに「暗黒星」のような本格ミステリー調のものも紛れ込んでいて、とても驚いた記憶がある。
それがおそらくミステリーとの最初の出会いである。
同じように少年探偵団シリーズからミステリーに入った作家も多いようだ。
2. アガサクリスティの本格ミステリー
次のステージはアガサクリスティの「ABC殺人事件」。見立て殺人モノの原点と言える作品である。
この作品をきっかけに意外な犯人やトリックの面白さを知って、ミステリーにハマっていった。
しばらくはアガサクリスティばかり読んでいて、当然「そして誰もいなくなった」、「オリエント急行殺人事件」、「アクロイド殺し」の3名作の洗礼を受けた。
特に「そして誰もいなくなった」を読んでいるのが前提のミステリー小説がたくさんあるので、ミステリー読みの教養として読んでおく必要があるだろう。
ここで「ミステリー=トリック」という図式が自分の中で確立された。
3. 金田一少年の事件簿
そのころにマガジンで連載されていた「金田一少年の事件簿」のブームがあった。
本格的な物理トリックが主体で、ミステリーマンガという新ジャンルが確立されたように思う。
いろいろな有名ミステリーからのパクリが問題になっているようだが、まだミステリー初心者だった自分は大いに楽しんでいた。
4. 宮部みゆきの社会派ミステリー
その次の新しい出会いは宮部みゆき。
「火車」を読んで、トリックのない社会派ミステリーというジャンルがあることを知る。
人間ドラマを中心としたストーリー重視のミステリーである。
本格ミステリーはストーリーが面白くないものが多かったので、こんなジャンルがあることに驚き、「ミステリーに必ずしもトリックは必要ない」ということを学んだ。
ミステリー要素はストーリーを面白くするための味付け。
そこから「模倣犯」など宮部みゆきの作品や、東野圭吾の「白夜行」など、社会派ミステリーを読破していった。
5. 綾辻行人・新本格の衝撃
その後しばらくミステリーから離れていたのだが、ある時にふと手に取ったのが綾辻行人の「十角館の殺人」。
以前好きだったアガサクリスティの「そして誰もいなくなった」をベースにしたミステリーで、ラストがどう違うのか気になりながら読んでいたが…。
トリックに強い衝撃を受けたことを今でも忘れられない。
こんな面白い小説が世の中にあるのか…!。
「十角館の殺人」は日本のミステリー界に大きな影響を与え、本格ミステリーのブームを作った歴史的な作品。
やっぱり社会派より本格ミステリーの方が面白い。
この作品をきっかけにして、本格ミステリーに回帰した。
まとめ
小説は作者の自己表現のための作品も多いが、ミステリーは「読者を驚かせたい、楽しんでもらいたい」というモチベーションから書かれている。
本格ミステリというのは、あらゆる小説ジャンルの中で一番読者を意識している小説だと思う。
「ミステリを書く」より
つまりミステリーは小説の中で一番読者のために作られていると言えるだろう。読まない手はない。
そこから色々なミステリーを読み漁って今に至る。
次回はそんな中から、おすすめのミステリー小説ベスト10を紹介する。
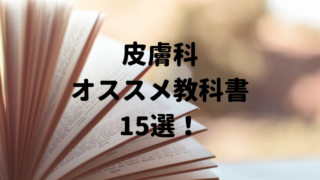
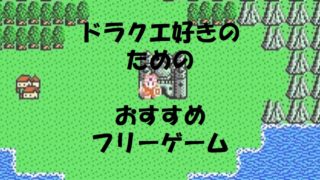
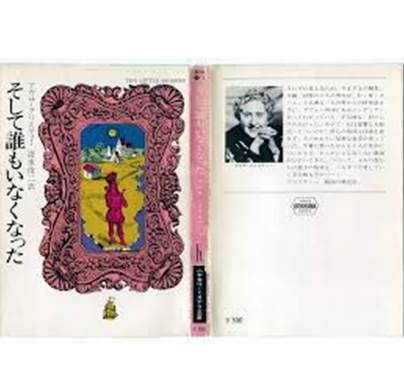








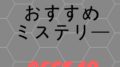
コメント