面白い医学書を多数執筆されている國松淳和先生。
これまで色々な本を紹介してきた。

國松先生の最新刊が出版されたので、遅まきながら購入。
今回は流行りの鈍器本である。
様々な疾患の雑感がひたすら記載されているという、クセの強い一冊に仕上がっている(約1700p)。
「教科書にはこう書いてあるが、私はこうしている」みたいな経験則が好きな自分にとっては、たまらない内容だった。
その中で面白かった疾患を10個選んでみた。
①「COPD」
治療のアドヒアランスに関する記載が目を引いた。
「吸入の手応えがないことがアドヒアランスの低下を招いている」
こういう一般的な教科書には書かれていないことが、実臨床では一番大事だったりする。
吸入時に吸入の手応えがなく「吸入できた気がしない」などという治療に関する小さな後ろ向きの心理の積み重ねがあると個人的には思っている。
「それで吸入できているんですよ」と他者が励ますのは当然である。
あと「専門医が非専門医に対してハードルを上げない」という視点も大切にしたい。
呼吸器内科医だけでCOPD患者を診ていくには限界がある。
「専門医が非専門医に対してハードルを上げない」という点がおそらく重要
非専門医の診療に文句ばかり言う専門医も多いので…。
②「上部消化管出血」
消化器内科医への不満がひたすら書いてあって面白かった。
問題はたくさんある。なかでも一番は、オンコール医のみたてや判断の差にあまりに開きがあることである。
あれはやったかこれをやっとけと電話口でうるさく、態度も悪い人物が多い。
よっぽど嫌な思いをしたんだな、というのが伝わってくる。
具体的な対策は心の中で毒づくこと(笑)。
対策としては、心の中で「お前から内視鏡をとりあげたら何が残るのか」を考察してみるとよい。
③「機能性消化管障害」
こういう器質的ではない疾患は國松先生の得意分野(たぶん)。
機能性消化管障害は「機能性ディスペプシア」や「非びらん性逆流性食道炎」などを包括した概念らしい。
器質的とはいえない消化管障害があり、それが患者にとって不快であるときに機能性消化管障害と呼ぶと便利である。
PPIに加えて、漢方薬やプレガバリン、スルピリドなど様々な手を組み合わせて治療していくようだ。
検査で異常所見がないので「診断が曖昧」で、「決定的な治療法がない」疾患に対する真摯な取り組みは参考になる点が多い。
④「良性発作性頭位めまい症」
対症療法の重要性が強調されているのがポイント。
頭部を動かすことに恐怖している患者に「行動」を処方しているのである。
なんでもいいので、特に初発の良性発作性頭位めまい症では1週間処方して再診させて確認してあげるとよい。
エビデンスがなくても、「何かやることがポジティブな効果を生む」というのは意識しておきたい。
⑤「2型糖尿病」
アドヒアランスが悪い患者が多い印象だが、教条的ではない態度がポジティブな効果を生むかもしれない。
「ちゃんとできてなくていいから、また来てもらうことが大事」
ちゃんとできなくていいから「また来てもらう」ような関わりが、糖尿病診療の導入では最適である。
薬物治療を拒否した場合でも、「食事に気をつけましょう」と言ったことで、塩分摂取量が減って血圧が下がるかもしれない。
外来診療には柔軟性も必要である。
⑥「脂質異常症」
ガイドラインと実際の臨床の乖離が指摘されている。
現場では実に簡素であるにもかかわらず、ガイドラインではそれに比してとんでもなく込み合っていて重厚なのである。
ここまで現状と学会レベルで推奨する内容が乖離するのもめずらしい。
実臨床で役に立たないガイドラインというのは少なくない。
どうやったらアドヒアランスが上がるかといった記述についてはほとんどなく、唯一「動機づけ面接」が有用である、とあった。
しかし、動機づけ面接とは何か、どう実践するか、といった事柄の記述は皆無だった。
ガイドラインだけでは実際の診療はできないということである。
⑦「気管支喘息」
やはりアドヒアランスが重要という話。
極論すれば薬の使い分けなんてあってないようなもの。
診療の努力の多くはこの、いかに継続できるか。どうしたら毎日治療してくれるか、に費やしたほうがいい。「薬の使い分け」などあってないようなものである。
皮膚科でも、どの外用薬を選択するかよりも、ちゃんと外用してもらえるかが重要なので、納得感が強い。
⑧「薬疹」
おなじみの皮膚科ディスりは健在。
消化器内科医に対しては心の中で毒づくだったが、皮膚科医に対しては遠慮がなく痛快である。
薬疹の診断は皮膚科医が下すとは限らない。どちらかというと、担当医が下す。
皮膚科医は、皮膚のパターン(薬疹で矛盾しないか)の判定と、薬疹以外の皮膚疾患の可能性を考えるという役割であって、つまりは脇役である。
実際、薬疹は臨床診断なので、皮疹だけ見せられてもよく分からないのである。
臨床経過が診断に直結するため、経過を把握している主治医のほうが診断できるというのは間違っていない。
⑨「高齢発症関節炎」
高齢発症の関節リウマチを本書では「高齢発症関節炎」としている。
昔、PMRっぽい高齢患者が、血清反応陰性関節リウマチという診断になったのを見て、よくわからなかった。
実際、PMRと高齢発症関節リウマチは区別できないものらしい。
完全に本症とPMRを区別しきることは初診時にはできない。
國松先生はその後の経過から鑑別していくそうだ。
ステロイド減量目的にメトトレキサートやタクロリムスを併用しようと思ったとき、その瞬間それはPMRではなくはじめから高齢発症関節炎だったとするという考え方である。
こう認識してから、外来診療で何も迷わなくなってしまった。
このように「明確に診断名がつけられない病態」を言語化する試みは有用だと思う。
皮膚科でもよくあるシチュエーションである。
⑩「成人スティル病」
成人スティル病の実際。
除外診断のレトリックが暴かれているのが面白い。
「成人スティル病は除外診断である!」というのは、建前上は確かにそうだが、これが詭弁であることを見抜かなければならない。
「除外診断する疾患」同士が互いに鑑別対象となっていたらどうなるのであろうか。
このへんの臨床診断の感覚は大切にしたい。
まとめ
今回は國松先生の鈍器本を紹介した。
読み物として通読するような内容を、通読できない分量で出したという点で唯一無二の本である。
國松先生の経験則は、皮膚科診療にも応用が効く場面が多い。
皮膚科でもこんな奇書が登場してほしいものである。


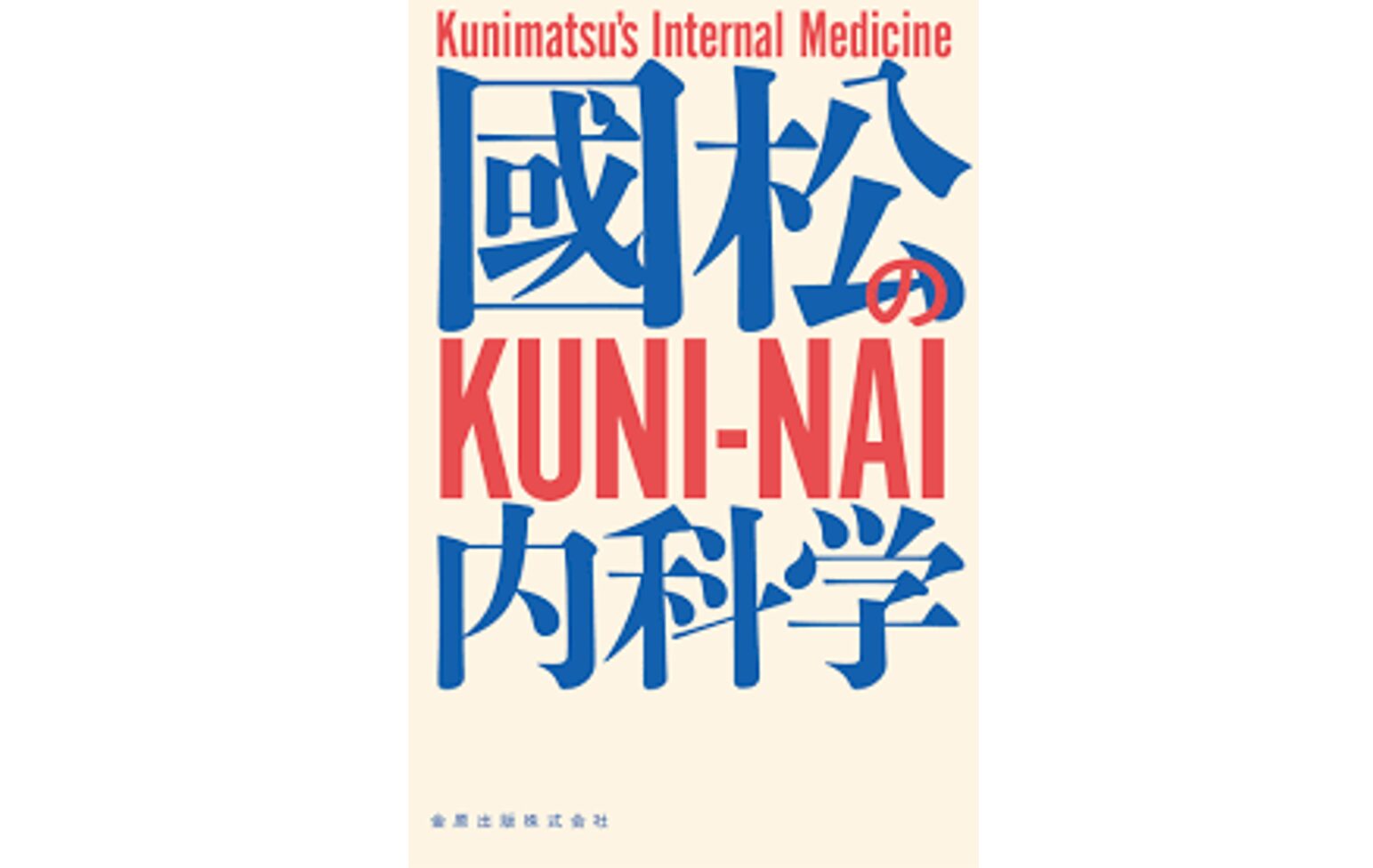


コメント